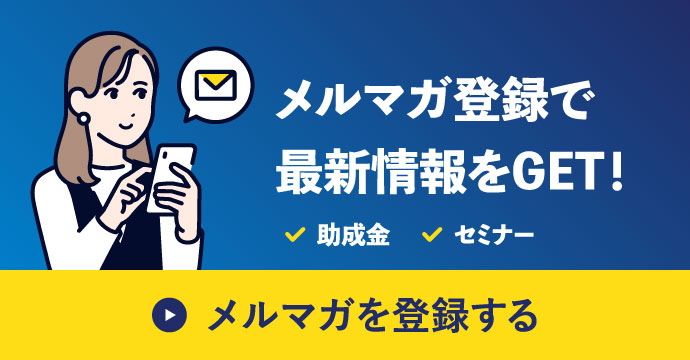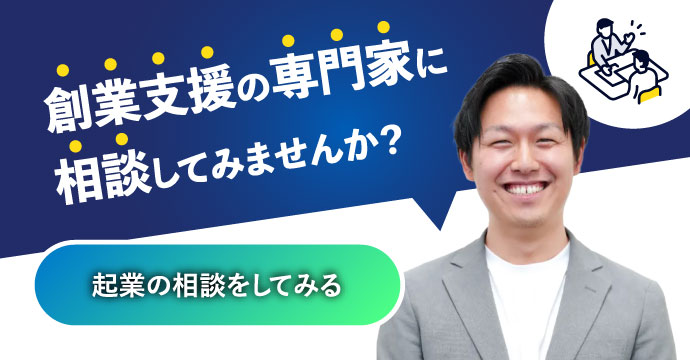宮城県には、人口減少や商店街の空洞化、若者や女性の都市部流出、交通課題、不登校、災害リスクなど、さまざまな地域課題があります。一見すると「大きな問題」に見えるこれらのテーマも、見方を変えれば、起業や活動のヒントに満ちています。
ここでは、地域の今と向き合うための6つの視点をご紹介します。
防災

宮城県は、地震や津波、豪雨などの自然災害が多発する地域です。
特に2011年の東日本大震災では、最大遡上高が20メートルを超える津波により、沿岸部を中心に甚大な被害を受けました。その後、道路や防潮堤などのハード整備が進められましたが、近年は気候変動の影響により、短時間強雨の発生が増加し、洪水や土砂災害のリスクが高まっています。
また、令和元年の東日本台風では、山間部や沿岸部で道路ネットワークが寸断され、集落の孤立や物流の停滞など、地域経済にも大きな影響が出ました。
これらの課題に対応するため、宮城県では「第五次地震被害想定調査」を実施し、最大クラスの津波による死者数を今後10年間で約8割減少させるなどの減災目標を設定しています。
ハード整備に加え、地域住民の防災意識向上や避難行動の強化など、ソフト面での継続的な取り組みが求められています。(参考:「宮城の道づくり基本計画」令和3(2021)年3月策定)
3.11後のハード整備は一段落したものの、継続的な防災・減災への取り組みが必要不可欠です。
参考:https://www.pref.miyagi.jp/documents/14922/siryou2-1.pdf
不登校

東北・宮城県は小中学生における不登校について長年、全国的に高い数字で推移しています。
令和5年度の文部科学省調査結果(宮城県分)では、不登校出現率が小学校2.74%(全国2.14%)、中学校8.32%(全国6.71%)で、いずれも依然として全国平均を上回っています。
児童生徒一人ひとりが抱える課題は多様であり、その背景や事情も異なります。
そのため、個々の状況に寄り添った支援策の充実と継続的な取り組みが求められます。
参考:https://www.pref.miyagi.jp/site/gikyou-kkr/reserch-on-problems.html
交通弱者

宮城県の「過疎地域持続的発展計画」によれば、2市9町の過疎地域市町村と4市1町の一部過疎地域市町村が存在します。
県内におけるこうした過疎地域では、住民バスなどだけでは高齢者などの交通弱者の交通手段が十分確保されていない地域が存在することや、過疎地有償運送が実施されていない状況です。
公共サービスだけでなく、民間サイドからのサービスも含めた課題解決が必要な課題領域となっています。
参考:https://www.pref.miyagi.jp/site/tiikisinnkou/kasotiiki.html
中小企業における後継者不足と事業継承

2024年版中小企業白書によると、中小企業の経営者年齢は高齢化が進んでいます。
2000年の経営者年齢ピークは「50~54歳」でしたが、2015年には「65~69歳」、2023年には「55~59歳」へと移動し、経営者年齢の分布は平準化しています。
一方で70歳以上の経営者の比率は過去最高となっており、依然多くの企業で承継が必要です。
後継者不在率は2018年以降低下傾向にあるものの、2023年時点で54.5%の企業で後継者が未定となっています。
このままでは多くの企業が廃業に追い込まれ、雇用や地域経済に影響が出る恐れがあります。
事業承継の準備には5~10年かかるとも言われており、早めの検討が急務です
中小企業庁「事業承継診断」
商店街の空洞化に関する課題

宮城県が実施した令和5年度商店街実態調査(令和5年10月1日現在)※ によると、県内商店街の景況感は依然として厳しい状況が続いています。
商店街が直面している主な課題としては、「後継者不足」が最も多く66.9%、次いで「商圏人口の減少」(41.9%)、「集客力のある店舗・業種が少ない又は無い」(36.9%)が挙げられています。これらの課題は、商店街の活性化を阻む要因となっています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響も依然として深刻であり、約8割の商店街が「イベント等の延期・中止」や「来街者の減少」、「営業自粛等による売上の減少」を経験しています。これらの影響は、商店街の経営環境に大きな打撃を与えています。
これらの課題に対処するためには、後継者の育成や商圏人口の維持・拡大、魅力的な店舗や業種の誘致など、総合的な取り組みが求められます。
また、地域住民や行政、関係団体が連携し、商店街の活性化に向けた具体的な施策を講じることが重要です。
※参考: https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/syoutengai-zittai-survey.html
ジェンダーギャップと若い女性の流出

都道府県版ジェンダー・ギャップ指数(2025年度)※によれば、宮城県のジェンダーギャップ指数は都道府県別で行政分野で37位、教育分野で16位、政治分野で6位、経済分野で21位という結果でした。
経済分野について詳しく分析すると、フルタイムの仕事に従事する割合の男女比が21位と比較的高い順位にあるのに対して、フルタイムの仕事に従事する男女間の賃金格差は29位に留まっています。
県内における若年層女性は、東京圏に流出し続けています。
進学や就職時期といったターニングポイントにあたる時期に、女性の賃金の低いところから高いところへ経済的な地位を見越して移動していくことが大きな理由です。
こうした賃金格差を埋めていくための施策を、行政・民間、双方連携の上で実施していく必要があります。
また、宮城を取り巻く特徴として、仙台圏を中心とした支店経済特有の事情を考慮する必要があります。
配偶者の方の転勤に伴い、スキルがあっても会社を退職し配偶者の転勤先である宮城にいらっしゃる主婦の方々が多くいらっしゃる一方で、そうした方々がスキルを十分に生かして活躍できるフィールドはまだ十分に整備されているわけではありません。
彼女たちの活躍のフィールドをいかに拡張していくか、という課題が存在します。
※参考:https://digital.kyodonews.jp/gender2025/data/4
これらの地域課題は、一見すると大きな壁に見えるかもしれません。
けれども、視点を変えれば、地域の未来を自らつくるためのヒントや、事業の種が詰まっています。地域の「いま」に目を向けてみることから、次の一歩が始まります。